電験二種とは?試験内容・難易度を徹底解説!
目次
電験二種とは?資格のと特徴を解説

電験二種(第二種電気主任技術者)は、電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物を保守・監督するための資格です。国家資格である電気主任技術者の中で中級レベルに位置し、発電所や変電所、工場、ビルなどの電気設備を管理する重要な役割を担います。
本記事では、電験二種の正式名称や資格の位置づけ、電験三種・電験一種との違いについて詳しく解説します。取得を目指す方は、まず資格の概要をしっかり理解することが大切です。
電験二種の正式名称と位置づけ【電気主任技術者の中での役割】
電験二種の正式名称は「第二種電気主任技術者」であり、電気設備の保守・管理を行う国家資格です。この資格を取得すると、最大17万ボルト未満の事業用電気工作物の監督業務を担当できます。
電気主任技術者は、電気事業法に基づき、以下のような事業用電気工作物の管理を義務付けられています。
- 発電所(火力・水力・再生可能エネルギー発電所など)
- 変電所(高圧電力を受電し、低圧に変換する設備)
- 工場・プラント(電力を大量に消費する生産施設)
- ビル・商業施設(オフィスビル・ショッピングモールなどの大型建築物)
これらの設備は、安定的に電力を供給するために適切な運用・保守が不可欠です。そのため、電気主任技術者の選任が義務化されており、電験二種の資格保持者は、こうした重要な現場での監督業務を担うことになります。
電験二種は電験三種よりも高度な知識を求められ、より大規模な電力設備を扱うことができる点が特徴です。一方で、電験一種と比べると扱える設備の範囲は制限されますが、電力業界でのキャリアアップを目指す上で非常に有利な資格といえます。
電験三種・電験一種との違い【資格の比較】
電気主任技術者の資格は第一種・第二種・第三種の3種類に分かれており、それぞれ監督できる電気工作物の範囲が異なります。以下の表にまとめました。
| 資格 | 監督できる範囲 | 主な就職先 |
|---|---|---|
| 電験三種 | 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物 (例:オフィスビル・小規模工場) |
ビルメンテナンス会社、工場、商業施設の設備管理 |
| 電験二種 | 電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物 (例:発電所・変電所・大規模工場) |
電力会社、大規模工場、エネルギー関連企業 |
| 電験一種 | すべての事業用電気工作物 (例:大規模発電所・全国送電網) |
電力会社、エネルギー企業、インフラ企業 |
電験三種は最も取得しやすい資格で、主に小規模な電気設備を扱います。一方、電験二種は発電所・変電所などの大規模設備の管理が可能となり、電力会社や大企業での活躍が期待できます。電験一種はすべての電気設備を監督できる最上位資格であり、全国レベルの電力インフラの管理に関与することができます。
試験の難易度も電験三種 < 電験二種 < 電験一種の順で高くなります。特に、電験二種は一次試験と二次試験の両方に合格する必要があり、記述式の試験が含まれるため、より専門的な知識と応用力が求められます。
電験二種を取得すると、電験三種では扱えない大規模な電力設備を管理できるため、企業内での昇進や転職の幅が広がります。特に、電力業界やインフラ関連企業では電験二種保持者の需要が高く、高収入を目指すうえでも有利な資格となります。
このように、電験三種・電験二種・電験一種は、それぞれキャリアのステップアップに応じた資格となっており、自分の目指す働き方や職場に応じて取得を検討することが重要です。
電験二種の試験概要【試験内容・受験資格・合格基準】

電験二種(第二種電気主任技術者)は、電圧17万ボルト未満の電気設備を保守・管理するために必要な国家資格です。この資格を取得すると、発電所・変電所・工場などの電気設備の保安監督を行うことができます。
試験は一次試験と二次試験の2段階方式で実施され、どちらにも合格することで資格を取得できます。一次試験はマークシート方式、二次試験は記述式で行われるため、それぞれの試験形式に適した対策が必要です。
受験資格に制限はなく、学歴・年齢・実務経験の有無に関わらず誰でも受験可能です。ただし、試験内容の難易度が高いため、事前にしっかりとした学習計画を立てることが重要です。
合格基準については、一次試験・二次試験ともに60点以上が基本とされていますが、試験の難易度によっては調整される場合があります。また、一次試験には科目合格制度があり、一部科目に合格すると、翌年度および翌々年度はその科目が免除される制度が用意されています。
電験二種の試験方式【一次試験・二次試験の違い】
電験二種は、一次試験と二次試験の2段階で構成されています。それぞれの試験には異なる特徴があり、合格するためにはそれぞれに適した学習方法を取り入れることが重要です。
一次試験は、マークシート方式で実施され、4つの科目(理論・電力・機械・法規)から出題されます。合格基準は各科目60点以上とされていますが、年度によって若干の調整が行われることがあります。
二次試験は、記述式で行われ、「電力・管理」と「機械・制御」の2科目が出題されます。計算問題や論述問題が多く含まれ、試験時間内に正確な計算と適切な記述が求められるため、高度な理解と実践的な対策が必要になります。
また、一次試験に合格した場合、その年度の二次試験に不合格でも翌年度は一次試験が免除され、二次試験から受験することが可能です。
一次試験の試験科目と出題範囲
電験二種の一次試験は、4科目(理論・電力・機械・法規)で構成され、それぞれ異なる分野の知識が問われます。試験内容は電験三種の延長ではあるものの、難易度が大幅に上昇するため、しっかりとした対策が必要です。
理論【計算問題の多さと難易度】
理論科目では、電気理論・電子理論・電気計測が問われます。この科目は、一次試験の中でも最も難易度が高いとされ、多くの受験生が苦戦するポイントです。
特に、微分積分・ベクトル解析・ラプラス変換などの数学的な知識が必要であり、数学が苦手な人にとっては高いハードルとなることが多いです。また、計算問題の比率が高いため、公式を暗記するだけでなく、計算のスピードと正確性を上げる必要があります。
過去問を解く際は、途中計算の過程までしっかりと理解し、ただ答えを覚えるのではなく、計算の原理を理解することが大切です。
電力【発電・変電・送電・配電に関する知識】
電力科目では、発電・変電・送電・配電に関する知識が出題されます。電験三種でも学ぶ内容ですが、電験二種ではより高度な計算問題が出題されるのが特徴です。
特に、発電設備の構造や運転原理、送電線の電圧降下や電力損失、電力系統の安定運用など、電力会社や工場で実際に活用される知識が求められます。
また、電力需要と発電量のバランス、再生可能エネルギーの導入による系統運用の変化など、近年のトレンドにも注目することが重要です。
機械【パワーエレクトロニクス・自動制御】
機械科目では、電気機器・パワーエレクトロニクス・自動制御に関する知識が問われます。出題範囲が広いため、計画的に学習を進めることが重要です。
特に、誘導電動機・同期機・変圧器の動作原理や特性、電力変換装置(インバータ・コンバータ)の動作原理についての理解が必要です。また、近年では自動制御理論の比重が高まっており、フィードバック制御・伝達関数・ラプラス変換の知識も求められます。
計算問題も多いため、過去問を活用しながら、公式の使い方や計算過程をしっかりと理解することが大切です。
法規【電気法規と保安管理】
法規科目では、電気事業法・電気設備技術基準・保安管理に関する内容が出題されます。他の科目と異なり、暗記が中心となるため、確実に得点できるように対策を進めましょう。
特に、電気主任技術者の職務と責任、保安規定、電気設備の安全管理に関する知識は、実務でも活かせる重要な内容です。また、計算問題として電力損失の計算や短絡電流の計算が出題されることもあります。
効率的に学習するためには、過去問を繰り返し解くことが有効です。条文を丸暗記するのではなく、具体的な適用事例と関連付けながら学習することで、より深い理解が得られます。
二次試験の試験科目と出題範囲
電験二種の二次試験は記述式で行われ、一次試験よりも深い知識と応用力が求められます。出題範囲は広く、単なる暗記だけではなく、理論の理解と実務での活用力が問われます。
二次試験では、「電力・管理」と「機械・制御」の2科目に合格する必要があります。それぞれの科目で、発電・送電・制御技術など、電気主任技術者としての実践的な知識が試されます。
以下、それぞれの試験科目の出題範囲について詳しく解説します。
電力・管理【発電所・変電所の設計と運用】
「電力・管理」は、発電所や変電所の設計・運用に関する高度な知識を問われる科目です。電力供給の安定性を確保するための技術や、エネルギー効率を最大化する設計について深く理解しておく必要があります。
この科目では、以下のような内容が出題されます。
- 発電方式の特徴と選定(火力・水力・原子力・再生可能エネルギー)
- 変電設備の構成(変圧器・遮断器・保護リレーなど)
- 電力の安定供給技術(負荷変動対策・電圧調整・周波数制御)
- 電力系統の保護と管理(系統安定化・事故時の対応策)
特に、近年では再生可能エネルギーの普及が進んでおり、風力発電や太陽光発電の特性、導入時の課題なども出題される可能性が高いです。
また、電力設備のメンテナンス計画や設備投資の最適化についても問われることがあるため、電気主任技術者としての視点を持って問題を解くことが重要です。
機械・制御【電気機器と制御技術】
「機械・制御」は、電気機器の基本構造や動作原理に加え、自動制御技術についての知識が問われる科目です。特に、電動機や変圧器の動作、パワーエレクトロニクス技術、制御工学の基礎などを深く理解することが求められます。
この科目で出題される主な内容は以下の通りです。
- 電動機の特性と運転(誘導電動機・同期電動機・直流電動機の違い)
- 変圧器の動作と応用(変圧比・損失計算・負荷試験)
- パワーエレクトロニクス技術(インバータ・コンバータ・チョッパ制御)
- 自動制御の基礎(PID制御・フィードバック制御・ラプラス変換)
この科目では、特に計算問題が多く出題される傾向があります。例えば、電動機の回転速度の計算や、トランスの効率計算、制御系の応答解析などが頻出です。
また、近年ではスマートグリッド技術やエネルギーマネジメントシステム(EMS)に関する問題も出題されることがあり、最新の技術動向にも注意を払う必要があります。
この科目の攻略には、公式の暗記だけでなく、実際の電気機器がどのように動作するのかを理解することが重要です。過去問を解く際も、単なる解答の暗記ではなく、計算のプロセスや理論の背景を意識しながら学習すると、より確実に合格へ近づくことができます。
電験二種の難易度と合格率【データから分析】

電験二種は電気主任技術者としてのスキルを証明する難関資格の一つです。試験は一次試験と二次試験に分かれ、それぞれの合格基準を満たさなければなりません。
特に二次試験の記述式問題は難易度が高く、単なる知識ではなく応用力が求められます。そのため、試験の特徴を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
この記事では、過去5年間の合格率データを分析し、各科目ごとの難易度と効果的な学習法について詳しく解説します。
一次試験と二次試験の合格率【過去5年の推移】
電験二種の合格率は、年度によって変動があるものの、一次試験・二次試験ともに低い合格率を維持しています。特に二次試験は、記述式ということもあり合格率がより低くなる傾向です。
| 年度 | 一次試験合格率 | 二次試験合格率 |
|---|---|---|
| 2020年 | 27.2% | 27.9% |
| 2021年 | 25.7% | 17.2% |
| 2022年 | 35.2% | 24.0% |
| 2023年 | 24.5% | 17.7% |
| 2024年 | 28.9% | 18.9% |
このデータから分かるように、一次試験の合格率は約25〜35%程度と比較的安定しています。しかし、二次試験は10%台後半〜20%前後と厳しい数値です。
特に二次試験では、記述式の解答が求められるため、解答の正確さだけでなく、論理的な表現力も必要になります。
試験科目ごとの難易度と対策ポイント
電験二種の試験科目は、一次試験が4科目、二次試験が2科目で構成されています。中でも「理論」科目の合格率が低いことが特徴です。
理論科目の攻略方法【合格率が最も低い科目】
理論科目は、電験二種の一次試験の中でも最も合格率が低い科目として知られています。過去のデータによると、理論科目の合格率は16〜20%程度と他の科目に比べて低くなっています。
この科目が難しい理由は、次のようなポイントが挙げられます。
- 数学的な要素が多く、微分積分やラプラス変換などの知識が必須
- 問題の出題パターンが多岐にわたり、単純な暗記では対応しにくい
- 電験三種よりも高度な電気理論が求められる
攻略のためには、以下の対策を取りましょう。
- 数学の基礎をしっかり固める(特に微分積分・線形代数)
- 公式の暗記ではなく、なぜその公式が成り立つのか理解する
- 過去問を活用し、パターンごとの解法を身につける
特に過去問演習が鍵となるため、直近10年分の問題を徹底的に解くことをおすすめします。
二次試験の記述問題対策【計算力と論述力が求められる】
二次試験は計算問題と論述問題の両方が出題されるため、幅広い対策が必要です。合格率が低い理由として、以下の点が挙げられます。
- マークシートではなく記述式のため、解答の正確性が求められる
- 計算過程を明確に記述しないと、減点対象になる
- 論述問題では、論理的かつ簡潔な文章を書くスキルが必要
対策としては、以下の方法が有効です。
- 計算問題の演習を繰り返し、途中式も正しく書く練習をする
- 論述問題は、模範解答を参考にしながら記述練習を行う
- 試験と同じフォーマットの答案用紙を使い、時間を計って解答する
特に記述問題の書き方に慣れることが重要です。採点基準を意識しながら、論理的な解答を心がけましょう。
一次試験免除制度の活用【合格への戦略】
電験二種には一次試験免除制度があり、これを活用することで合格の可能性を高めることができます。
この制度の概要は以下の通りです。
- 一次試験の科目合格は2年間有効
- 全科目合格した年度の翌年は、一次試験免除で二次試験のみ受験可能
この制度を最大限に活用するためには、以下の戦略が有効です。
- 1年目に理論と機械、2年目に電力と法規の合格を目指す
- 2年以内に全科目合格し、3年目は二次試験対策に集中する
- 一次試験の合格科目を活かしながら、計画的に学習を進める
このように免除制度を活用すれば、学習負担を分散させながら効率的に合格を目指せます。
電験二種は難易度の高い試験ですが、正しい学習計画と対策を立てれば、十分に合格は可能です。自分に合った学習法を見つけ、計画的に取り組みましょう。
電験二種に合格するための勉強法と対策
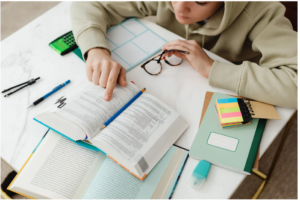
電験二種の試験は、高い専門知識と応用力が求められるため、効率的な勉強方法を実践することが重要です。特に、一次試験・二次試験ともに出題範囲が広く、それぞれに適した学習戦略が必要になります。
ここでは、電験二種に合格するための勉強法について、必要な勉強時間の目安や独学と講座利用の違いを詳しく解説します。また、一次試験の突破方法についても、具体的な学習法を紹介します。
必要な勉強時間の目安【独学・講座利用の違い】
電験二種の合格には、十分な勉強時間の確保が必要です。一次試験と二次試験を含めると、合計400時間~600時間程度の学習が目安とされています。
しかし、電験三種の合格者と未経験者では、必要な学習時間に大きな差が生じます。以下の表を参考に、自身の状況に応じた勉強計画を立てましょう。
| 受験者の状況 | 必要な勉強時間(目安) | 学習のポイント |
|---|---|---|
| 電験三種を取得済み | 約400時間 | 二次試験対策を重視 |
| 電気系の学科卒業者 | 約500時間 | 一次試験の理論・機械を重点的に |
| 電気の基礎知識がない | 約700時間 | 電験三種レベルの基礎固めが必須 |
独学で学習する場合、参考書や過去問を活用しながら、自分でスケジュールを組み立てて計画的に進める力が求められます。一方、講座を利用する場合、体系的なカリキュラムに沿って効率的に学習できるメリットがあります。
一次試験突破のための勉強方法は講座がおすすめ
一次試験は、マークシート方式の選択問題で構成されています。しかし、計算問題や応用問題が多く、単なる暗記では対応できません。そのため、理解を深めるための学習が必要です。
講座がお勧めな理由
電験二種の一次試験対策として、通信講座やオンライン講座を活用するのが効果的です。特に、以下の理由から講座を利用するメリットは大きいと言えます。
- 学習カリキュラムが体系的に整備されているため、学習計画を立てやすい
- 解説動画や模試が充実しているので、独学よりも理解が深まりやすい
- 疑問点を講師に質問できるため、効率的に学習を進められる
- 過去問の解説が充実しているため、試験傾向を把握しやすい
また、通信講座ではオンラインでいつでも学習ができるため、仕事や家庭と両立しながら勉強を進めやすい点も魅力です。特に、初学者や独学に不安がある方には、講座を活用することをおすすめします。
独学でも不可能ではない
講座を利用するのが効率的とはいえ、独学でも十分に合格を狙うことは可能です。ただし、自己管理能力と適切な学習計画が必要となります。
独学で合格を目指す場合、以下のポイントを意識すると効果的です。
- 信頼できる参考書を選ぶ(電験二種専門のテキストを活用)
- 過去問を徹底的に解く(5~10年分の問題を解くのが理想)
- 学習スケジュールを厳守する(1日2~3時間の学習を習慣化)
- 理解できない部分を放置しない(解説書やネットで調べながら進める)
独学は自由度が高い反面、途中で挫折するリスクもあります。そのため、計画的に進められる人や、すでに電気の基礎知識がある人には向いている方法と言えるでしょう。
結論として、短期間で確実に合格を目指すなら講座の利用、コストを抑えて自分のペースで学習したいなら独学という選択が適しています。
二次試験合格のための学習戦略
電験二種の二次試験は、記述式の試験であることが大きな特徴です。一次試験のマークシート方式とは異なり、論理的な解答が求められます。そのため、計算力・論述力の両方を鍛えることが合格への鍵となります。
二次試験は、「電力・管理」と「機械・制御」の2科目で構成されており、それぞれ専門的な知識を深く理解していることが求められます。特に、電力系統や電気機器の特性に関する問題は難易度が高く、過去問演習が重要になります。
ここでは、計算問題・論述問題・模試の活用という3つの視点から、効率的な学習戦略を解説します。
計算問題の解き方【電卓の活用と効率的な計算方法】
二次試験では、多くの計算問題が出題されます。特に、電力系統の負荷計算や三相交流回路の解析は頻出テーマです。これらの計算問題に対応するためには、正確かつ迅速な計算力が必要になります。
計算問題の効率的な解き方として、以下の3つのポイントを意識しましょう。
- 電卓を使いこなす:電験二種の試験では、電卓の使用が認められています。普段から試験で使用する電卓を使い、キー操作に慣れておきましょう。特に、指数計算・三角関数・対数関数の操作をスムーズに行えるようにしておくと、試験本番での計算スピードが向上します。
- 計算ミスを減らす:電験二種の計算問題は、途中過程の記述が求められることがあります。そのため、計算過程を明確に書き、見直しを徹底することが重要です。計算式を省略せず、単位や符号にも注意しましょう。
- 過去問演習を繰り返す:過去問を解くことで、出題傾向を把握できます。本番を意識した時間配分で演習することで、試験当日の時間管理がしやすくなります。
論述問題の対策【採点基準を意識した記述練習】
二次試験の論述問題は、試験官に分かりやすく説明する力が求められます。電気設備の設計や保守管理に関するテーマが多く、的確な解答を書くスキルが合格の鍵を握ります。
論述問題を攻略するためのポイントは以下の3つです。
- 採点基準を意識する:電験二種の論述問題では、専門用語を適切に使用し、論理的に説明できるかが採点のポイントになります。簡潔で明確な文章を意識しましょう。
- テンプレートを活用する:記述問題には一定のパターンがあるため、過去問の模範解答を参考に、解答の型を覚えると良いでしょう。「結論→理由→具体例」の流れで記述すると、論理的な文章になります。
- 手書きの練習を積む:試験では手書きで記述する必要があるため、実際に書く練習を行い、制限時間内に解答できるようにすることが重要です。文字のバランスや図解の描き方も意識しましょう。
模試・演習問題の活用法【本番を意識した対策】
二次試験の本番では、時間管理と問題の取捨選択が重要です。そのため、模試や演習問題を活用し、試験本番と同じ環境で練習することが合格につながります。
模試を効果的に活用するためのポイントを3つ紹介します。
- 試験時間を厳守する:本番と同じ時間制限内で問題を解く練習を行うことで、時間配分の感覚を養います。
- 苦手分野を明確にする:模試の結果を分析し、得点の低かった分野を重点的に復習することで、効率的な学習が可能になります。
- 本番のプレッシャーに慣れる:本番に近い環境で模試を受けることで、試験特有の緊張感に慣れ、実力を発揮しやすくなります。
模試の活用と過去問演習を組み合わせることで、試験本番でも落ち着いて解答できる実践力を身につけることができます。
二次試験は難易度が高いですが、適切な学習戦略を立てることで合格の可能性を大きく高めることが可能です。計算問題・論述問題の対策をしっかりと行い、模試を活用しながら本番に向けた準備を進めましょう。
まとめ|電験二種を取得してキャリアを広げよう

電験二種(第二種電気主任技術者)は、電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の監督を行うことができる国家資格です。取得することで、年収アップ・安定した職場環境・将来的な独立の可能性といった、多くのメリットを享受できます。
本記事では、電験二種の試験概要や難易度、勉強方法について詳しく解説しました。資格を取得することで、電気主任技術者としての市場価値を高めることができ、今後のキャリアに大きく役立ちます。
ここでは、電験二種を取得するメリットと、合格を目指すための具体的な勉強方法について詳しく解説していきます。
電験二種を取得するメリット【収入・安定・将来性】
電験二種を取得することで、収入面の向上・雇用の安定・将来性の確保といったメリットを得られます。具体的に、どのような利点があるのか見ていきましょう。
収入が大幅にアップする
電験二種を取得すると、電験三種よりも高い給与水準を得ることが可能です。企業の求人情報を見ても、電験三種の平均年収が400万~500万円程度であるのに対し、電験二種保持者の年収は600万~800万円に達することも珍しくありません。
さらに、電力会社やプラント企業、大手製造業では電験二種取得者に対して特別な手当を支給することが多く、手当だけで年間50万円以上の増収となるケースもあります。収入アップを目指すなら、電験二種は非常に有利な資格といえます。
雇用が安定し、定年後も働ける
電験二種を取得すると、電気主任技術者としての需要が高く、雇用が安定します。特に電力インフラを扱う業界では、電気主任技術者の確保が法的に義務付けられているため、景気の影響を受けにくい安定した職場で働くことが可能です。
また、電験二種を持っていると定年後もフリーランスとして活躍できます。企業と契約し、電気設備の保安監督業務を担当することで、60代・70代でも年収1,000万円以上を目指すことが可能です。
将来的な独立・フリーランスの道も開ける
電験二種を取得した後、一定の実務経験を積むと、「電気管理技術者」として独立開業が可能になります。独立すれば、自分で契約を取りながら仕事を進めることができ、年収1,000万円以上も狙えるようになります。
特に、電験二種保持者はビルメンテナンス業界や再生可能エネルギー関連の企業からのニーズが高いため、案件を獲得しやすいのも大きなメリットです。
自分に合った勉強方法で確実に合格を目指そう
電験二種は合格率が低く、難易度が高い資格ですが、適切な勉強方法を実践すれば、合格することは十分可能です。ここでは、自分に合った勉強方法を見つけるためのポイントを解説します。
一次試験と二次試験の違いを理解し、計画的に勉強する
電験二種は一次試験(マークシート)と二次試験(記述式)に分かれており、それぞれの対策が必要です。特に、二次試験の難易度が高く、独学では合格が難しいため、講座や参考書を活用するのが効果的です。
学習計画を立てる際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 一次試験対策では、過去問を中心に演習し、試験形式に慣れる
- 二次試験対策では、記述問題の解答例を研究し、論述の練習を行う
- 計算問題に強くなるため、電卓の使い方をマスターする
通信講座・オンライン学習を活用する
電験二種の試験範囲は広いため、独学だけでは効率よく学習を進めるのが難しいことがあります。そのため、通信講座やオンライン学習を活用するのも一つの方法です。
特に、以下のようなメリットがあります。
- 動画講義で分かりやすく学習できるため、理解が深まりやすい
- 学習スケジュールが決まっているため、モチベーションを維持しやすい
- 質問サポートがある場合、疑問点をすぐに解消できる
過去問を徹底的に解いて試験対策を行う
電験二種の試験は、過去問の出題傾向が似ているため、過去問題を解くことが非常に重要です。過去5年分の問題を解きながら、どの分野が頻出なのかを把握し、重点的に対策しましょう。
特に、以下の点を意識すると効果的です。
- 過去問を最低3回は繰り返し解く
- 間違えた問題は、解説を読んで理解し、同じミスを繰り返さない
- 模試を受けて、試験本番と同じ環境で演習する
電験二種は難関資格ですが、計画的に学習し、正しい方法で対策すれば、合格を十分に狙うことができます。
独学に不安をお持ちの方は、講座に参加して一緒に頑張りましょう!



